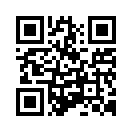なんかねぇ。
12月に入って慌ただしく、いろいろ勉強させていただく事も多く。。
うなってばかりのこのごろ。。
うううう、、ん。(ご心配なく、病気ではありません)
12月初めはなんと!静岡の会社のお手伝いをしました。
ジャトコさん。
トランスミッション(なんだそりゃ?)の展示会とシンポジウム発表のお手伝い。
シンポジウムを企画したことがありますが、
ここでは、それは、それは1000人ぐらい入るホールで、
なんだか豪奢なシャンデリアもついているし、
巨大なスクリーニングがあり、演題に立ったものは、カメラでばっちりと納められ
顔がアップ写しになるというもの。
会場にただ一歩足を踏み入れただけでも、足がすくんでしまう感じだ。
アシスタントの私でさえもそうだったから、発表する本人はもっとすごかっただろう。
バーン。

つぎつぎに招待を受けたパネラーが堂々と発表していく。
ドイツ人、アメリカ人などいたが、そのような西洋の人は
大勢の人の前で発表するということに慣れているし、
信じられないけれど、大抵の人がテキストを丸暗記しているか、
画像をみるとしゃべりたいことが、とうとうと出てくるのである。
しかも、どもったりすることや、いい間違いなしに。
そして、演題にかじりついていることにはあきたらず、
ずんずんと前の方に出て、観客に訴えかけたりするような人もいた。
そうなると、観客(といっても単なる人ではなく、専門家である)も話にのめりこんでいく、
私は、話の内容はチンプンカンプンで、右から左へ話が通り抜けて行った。
なにがすごいのか、なにが新しい事なのか、あるいは、大した事ない話なのか
分からなかったけれども、専門家ならわかるのよ。大したものねぇ。すごいねぇ。
さてさて、今回のご主人様の発表の順番がきました。
この発表前までに、何人かの日本人が小さなセミナー室で発表されたのも
聞く機会があったけれども。なんといっても、大人数前に発表することは慣れてないし、
しかも、慣れない言語にての発表はかなり発表している者にとっても厳しいものになっている。
おそらく、日本語と英語というのは音域が違うと思うの。
英語のリスニングが不得意っていうのは、よく聞くけれど
英語の音域に慣れていない性もあると思うし、
リスニングがちょっとぉ、というと、発音にも影響がでてくるのが実際だ。
英語のテキストを読んでいても英語に聞こえない、っていうのはとてもいたいところだ。
しかも、パネラーの発表の後、質問コーナーがあって、突然ふってわいてくるような質問に
的確に応対しなければならない。なんといっても、そういう態度も観客はみているのだ。
それで、おそらく、大した質問ではなくて、内容については簡単に答えられるのだろうけれど、
人の前に立つっていう緊張感などもあり、質問の内容があまりにも聞き取れないときがあるの。
そういうとき、もう一度お願いします。って頼むのは相手にとって失礼かなー。
と思ってしまって、仲間内で相談を始める。
仲間内で壇上で相談っていうのは、
西洋の人にはない。
もう一度お願いします、っといって
もう一度聞いたとしても、分からない時があるかもしれないけれど、
そういう時には、西洋人はちょっとまだよくわからないので、後ほど詳しくうかがってもいいですか。
なんて調子で対応してくる。といっても、やっぱり壇上で答えを述べた方が多くの人に聞いてもらえるし
一番いいにちがいない。
私は、決して別に西洋の人と同じようした方がいいといっているのではなく、
このビジネス一辺倒の世界で、文化差というものはまず横に置かれてしまう傾向があり、
自分たちの文化圏にはない予想外の行動であれば、会場が引いてしまったり、興ざめを運んでくる事がある。
内容はいいのだけど、なんか今一歩、心をつかんでないし、伝わってないみたいな
ことがあるのを、脇目に見る。
さてさて、こんな典型的な日本人の発表の例を見て、
今回、私が付いた方の番。
とにかく、最初ははらはらしましたがぁ。
ジョジョに演台に立っている自分に慣れていっている様子。
英語は日本語英語でございましたが、
かなり身振り手振り、ジェスチャーをいれられ、
しかもスクリーニングされていたから、効果も大。
緊張感はあるものの真剣さが現れた顔の表情も大写しで、
その、言葉以上にある情熱感が会場につたわることに。
大げさな大振りのジェスチャーは、マンガと通じ
彼は、サブカルで企業戦線をいっていると感じました。
新しいというか、これこそ、ヨーロッパにはない戦法
言葉足らずとも、会場を統括しておりました。
また、その後の小さなセミナーでは、
彼の会社の発表が、アメリカや日本の市場はかなり占めているのに、
ヨーロッパでの市場がまだなく、その市場開拓ができるように努力中だという発表。
ヨーロッパの道路事情や、彼らの運転の仕方の違いまで調べられていて
今後の展開を見守りつつあるとか。
さてさて、恐怖の質問コーナーがきちゃいました。
し、質問がやっぱり、き、聞き取りにくい。。。
もう一度お願いできますでしょうか。
と発表者が聞いて、もう一度質問をきいたけれどもぉ。
わ、わからない。
それで、みんなで相談を始めたけれども、
どうも分からないようだ。
後ろでそれを見ていた上司(私がついていた方)が
それを見かねて、あなたの質問はこう、こうこうでしょ。
と問いただした。
上司がでてくれば、なんのその。
それでは、その質問に関しましては、私が答えましょう。
関連会社、しかも日本資本でヨーロッパに進出してきた会社の社員が
これこれ、こいう訳でというのを出していた。
例え関連会社であっても、そういったことはヨーロッパの会社にはあり得ない。
自分以外の会社が援護に出て来ちゃうなんて。。
小さいことだけれど、日本企業の底力を見せつけてくれた感じだ。
普段、日本の美術や文化を紹介するような作業をしているけれども、
それ以上に、製品があり、それをどうにかして、
外国に受け入れてもらう努力をしている企業には、
文化の壁と摩擦がある。
それは厚く、熱いのだけれど。
最終的には、製品がよければよいだけ、信頼は生まれるだろう。
最初の製品が手に入る前が大変かもしれないけれども。
性能良い製品が創られる過程のように、コミュニケーションの中でも連携プレイは大事だ。
すんばらしい。
あんまり回転が良すぎて仕事が増えても困っちゃうだろうから、
ほどほどぐらいが丁度いいのだろうけれど。。ということをつけ添えていただいて。
それからドイツの働き方
言われたらやれ。
言われる前にやるな。
と日本の働き方
言わすな。
言われる前にやれ。
の間でいったりきたり、いったりきたり。
混乱して、大事な用事がぽーんと飛ぶ事も。
ごめんなさい。いけない、いけない。
次に戯画的オーバーアクションしている私をみつけたら
ああ、やってるなとお思いくださいませ。