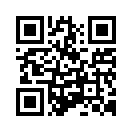日本のポスター展
がポツダムプラッツ、クルトアフォーラムにて行われている。
これは大日本印刷のコレクションとの共催で
ミュンヘン、チューリッヒ、フランクフルト、プラハを周り
ベルリンの次はワルシャワに巡回するという展覧会。
小さな展示であり、グラフィック特有の、宣伝ポスターはあまり多くなく、
商品のメッセージをダイレクトにイメージで伝えるという面白さはあまり目立たなかったけれど
日本のグラフィックの質のよさを押し出したものとなっている。
ビジュアルコミュニケーション(デザインの領域において)は、
やはり日本は先端をいっている。と思うのです。
文化的背景を理解していないとわかりにくいものがあるのだけれど、
わかりやすいっていうのかな。もちろんみんな一級の人だから
どれをとってもいいのでしょうけれど。
亀倉雄策さん、田中一光さんや福田繁雄さん
は特に、簡素明解で、すごいなーと思ったし、好きなグラフィックデザイナーですね。
この展示でポスターをみるのもよかったのだけど、
そこにあるビデオが、いいのよ。
キュレーションしたデザイン史研究家、柏木博さんが
今日第一線で活躍中のデザイナーにインタビューしていたものなのだけど。
柏木さんの物腰のやわらかい受け答えもよかった。
質問の中で最後に、若いデザイナーや、デザイナーを目指す若者に一言お願いしますという
お願いがあったのだけど
その中で、
青葉益輝さんは、
身体的能力
技術的能力
社会的適応能力 が必要だと。
机仕事のデザイナーが
身体的能力が必要というのにはびっくりしたけれど、
体の限界は、自分の才能も限界にするってことかな。
福田繁雄さんは、
ターゲットをみつける。
それは先輩ではない。同じジェネレーションの者だ。
先輩はすぐに倒れるから、皆と違う事をやっている人をみつけること、
音楽でも、文学でも。。
勝井三雄さんは。
現代をデザインするということは、
現代をみるということと、
もっと長いスパンをどう見ていくかということ。
松永真さんは、
自分の体験を素直に話すということ。
ということは、何か達成していないと話せない。
いろんなものを楽しむために収穫が必要。
目的や目標がわかっていれば、外すこともできる。
とにかく、基本が大切。
仲條正義さん
急げ。目の前のことで急いでくれ。間に合わない!
横尾忠則さん。
あまり迎合したりしない。流行にながされない。
出来るだけ流行に無関心になること。
他にも、もしグラフィックデザイナーにならなかったら
なにになりましたか?という質問もあり、
建築家や科学者、もしかしたら法律家になっただろうなぁ。
というだいたいの答えのなか、
横尾さんは、
やっぱりゆーびん屋さんかな〜。
好きですものいまでも。
大阪中央郵便局で一日局長やらせてもらったから
それで満足してますけど。
という答えが印象的でした。
Kulturforum Potsdamer Platz, Kunstbibliothek
15 June - 2 September 2007
9月2日まで。