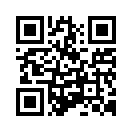日本に一ヶ月ほど帰っていました。
お知らせをしていなかった皆さんごめんなさい!
その間に以下の本を読みました。
以前より宗教には大変興味があり、とくに今は、多神教と一神教の違いについてです。
というのはその文化関連をつくる土台としてのものとしてその土地に根ざす宗教観念は
文化形成と切っても切り離せないものとなっていると思います。
ニーチェ以降、神は死んだ。と言われていても
つまり実質、宗教が現代において通用するかという議論をしなくても、
ここドイツにはキリスト教、あるいは歴史からいう
ユダヤ、そして最近の移民によるイスラムの影響がある
一神教的文化背景がまずはこんこんと流れていると考えています。
わたしの場合、ちょっとかわった表現をすれば、
多神教の国のアートを一神教の国の方に紹介するという
ようなこととも言えると思います。
畑がちがうところに出来上がった生成物を
ほいと、もってきたら、それは興味本位で見られることは確かだと思いますが、
それ以上にもっと根底にあるものを知ってほしいという願いがあります。
ですので、日々、わたしの日常はわたしの中に元々ない
相手の考えの素をさぐっているような状態です。
ですので、多神教と一神教の違いにとても敏感。
それに、なぜそこが違うかをわかれば、たとえ多神教からの生成物だろうと
一神教の文化背景をもつ方々へその受け入れ口を探すことも可能にも
なるでしょうし、わたしにとっても、そのとっかかりがわかることにもなってきます。
というかなり無謀な憶測があります。
ということで、沼津図書館で手に取ったものは、
本村 凌二さんの
多神教と一神教—古代地中海世界の宗教ドラマ (岩波新書) (新書)
読み進めると、古代ギリシャ・ローマは多神教だったのに
なぜそれが一神教化したのか、というとても興味深いテーマであることが
わかりました。
タイトルでこの内容が一度に把握できないのは残念。
そう、結構重要な疑問だと思います。
なぜ、多神教が一神教化したのかと。
今、手元に本がないので、要約というかわたしが理解したことを下に書きます。
昔の人は、ギリシャとかローマの人々が
やっていたということというのは、
神々に疑問を投げかけ「神託」を待ったと。
その神託通りに動いていたと。
それでその神託っていうのは、一種のひらめきで
今、脳科学的にいうと
それは右脳が処理している部分で、
なんとか問題を解決しようとする脳の働き。
ある程度、人は解決できない問題があると、
時間をおいて、自ら答えを見出していく生き物であるそうな。
たぶん、
自己治癒(自己治癒っていう言葉は本の中でつかわれてなかったですけれど)
が働くって理解してもいいのかなって思った。
神託って、自らの右脳力で答えをだしたもの。
最近の科学ってすごいって思ったけれども、
神の領域をも説明できることになったことについて。。
それでもって、なんで一神教に移行したかというと、
神々が沈黙しだした、
という表現を著者の本村さんは使用していたのですが、
つまり、簡単にいうと。
人が待てなくなったということなのです。
人が自分の中からでてくる判断を待つ時間がとれなくなった。
時代はそれだけ緊迫と緊急を要していたのでしょう。
人は早く神託がほしい状況が時代にあり、
そこが多神教から一神教への移行期だったと。
その時に人は人の内部ではなく、外に神を置いた。
しかも唯一の、だれにでも分かる共通の概念となるような。
この著書の本村 凌二さんの他の著書を調べると
歴史の専門家だということがわかります。
特に古代の。古代ヨーロッパの背景がごっそりわかっている人が
書く歴史書とはどんなものか、気になってきました。