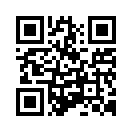母からの電話だったけれど。
ちょっと今、電話かけ直すからとして、
その質問には答えず。
あーあ。
この日を迎えました。
最後の母からの締めは。
もう、若くないという自覚をもって行動するように!
とのこと。
は、はーい!こ、こうちょうせんせい!
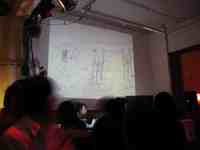
ユニット、ラ・コンディション・ジャポネーゼの
コンサートも重なり、ここにいなければならないので、
もしよかったら、来ていただきたいとの連絡を友達に。
コンサート会場隅にて小さく祝わせていただきました!

いただいたお手製チョコケーキを前にして。

それから、コンサート上パフォーマンスでつくっていた
市販スポンジに生クリームかけ。クマグミ上飾りのせも、”特別”いただきました!
お気遣いありがとうございます。(ところで私しか口にしませんでしたが。。)
本当は、飲み物売っているので、
厳禁ですが、オーガナイザーの一人
シンタローくんには、ロートケプシェン・シャンペンを用意していただいて!
これとコップをもっていっしょに祝いたいところの人にいってきなと
後押しをいただきました。
こう、なんていうの。
一升瓶をもって、しつこく飲ませちゃう人。
友達には、私が帰ろうというまで、つきあっていただいたような感じがします。
こちらでは、自分でお誕生日会をオーガナイズするので、
祝われるという感覚からいうとなんだか自分からいうのはなにかなーと思いますが、
どーしてパーティをしなかったのかなどと、苦情もうけることもあり。
ここは住んでいる人の国籍とか、生まれ育った国や宗教もばらばらだし、
また、外からきた私たちは移民みたいなもので、
ドイツの習慣とかも完全にわかってないまま、自分の国の習慣や気候や
肌に感じる空気とかも自分の国とは違うから節句とかも忘れがちになっている。
どんど焼きをオーガナイズする町内会なんてものはないしね。
だから、なんか儀式みたいなもの必要なんじゃないかと思って。