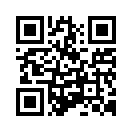週末はワルシャワの郊外へ。
電車でとことこ,遅れたりするけれども6時間ほどの旅です。

ロンドンの語学学校で一緒に勉強した方のお宅へ。
なんとも、ロンドン繋がりがこんなことに。。
近いからおいでよといわれ、
快諾してしまったわたしでした。
彼は銀行勤めの方で、能力が買われて転職をされるというので
前の職場と新しい職場の合間の一ヶ月自分の不得意分野を埋め合わせようと
ロンドンに語学留学されていました。
家族持ちで、妻と小さい子供がいると幸せそうに語っていたので、
しあわせそーだなぁと思いつつ、
てっきりワルシャワの郊外に住んでいる核家族のもとに招待をうけたかと思ったら、
4世代の同居の家で、ビックファミリーなところにお邪魔させていただくことに。。
そんなにお土産用意してこなかったよ〜と思いつつ。混じるわたし。
もうこの家に30年住んでいるということです。
にしても奇麗に掃除などがゆきとどいていて、新築といってもいいぐらいでした。
ということは自分の実家ってこと。
階ごとに分かれていて、
一番上は若夫婦
その下はおじいさんおばあさん夫婦
その下はひいおばあさんが住んでいます。
わたしは若夫婦のゲストだったので、
彼らの階に寝泊まりをさせてもらいました。
なんかねぇ。ポーランドの人は言葉が通じなくても、
一人にさせない感覚があって、ああ、こういう感覚はドイツにはないなぁ、
もしかしたら現代の日本にもないかもしれないものを見つけました。
逐一そばにいるという訳ではなく、一人でぷらぷらしていていても、
自分はこの家族に守られているし、たった二日で、単なる外国人で他人だったけれども家族として
迎えれてくれたという経験はすごいなぁ。と思った次第です。
最初言われた言葉は、
自分の家と思ってください。
ということだったし、
当たり前に食事がでてくるし、
当たり前に送り迎えがあるし、
当たり前に出るコストは主人持ちだったのです。
だんなさんは30前半の働き盛り
銀行マンで、ポーランドには国営と私営の銀行があるけれども
やはり勢いがあるのは私営の方だと。そんな私立の銀行に勤める彼。
これから国内でも一番、二番となるような銀行をめざし邁進中だとか。
そんな彼でも、昨今のポーランドの犯罪事情にはかなり危機感をもっていて
近代化、国際化していくワルシャワに自分が仕事上加担しながら
経済格差による、貧富の差がますます広がっていくのを大変危惧している方。
時には彼の家族にだってなにかしらの刃があたるかもしれないのです。
そういう会話が端々にでていた。
昔、自分の親は共働きをしながらも
まだまだ生活に余裕がなかったので、
土地を畑に開墾し、野菜を作っては売っていたという。
それも今は自分がいい職場についたので野菜は自分達のためだけのみ
に作っているといっていて、見ればなるほど。100ヘクタールほどの菜園が
広がっていた。すべて、無農薬野菜ということで

いや、これはとても豪華な生活だよ。
とわたしは言った。
彼の高収入のことをいったわけではなく、
自然食を食べながら健康に生きられる生活という意味だったのだけれど。
この豪華さはまだ彼には分からなかったらしい。
えりの言っていることは分からないと言われた。
2日目は
夕方から彼の知人の結婚式に出席。
知人の知人っていうことだから、わたしからいえば、ぜーんぜーん知らないお二人の
教会での結婚式に出席。
いいんでしょうか。
と思ったけれど。
あなたが来たいのであればどうぞと言われて
いきます。の返事をしたのは2週間前。
アベマリアがパイプオルガンで流れたりしていたけれども、
格式張ってはいず、カトリックの形式に従うということのみ。
その後は近くのレストランで祝賀会が行われた。
机にネームカードを発見して感激。し、知らない人なのに。。
そしてさすが、ポーランドです。
最初から、ウォッカでの乾杯があって。
なにかにつけ乾杯の音頭がある度にウォッカを注がれ。
ヒェーといいながらも、ウォッカと飲料水を交互に飲むはめに。。

食事は前菜がテーブルの上に山盛りに置いてあって
食べ尽くすことはできないほどに。
スープの後、メインの料理が2時間ごとに肉、魚、肉の順で3皿!。
最後の一皿はほとんどみんな残していたけれども。。
あとは、ダンス。ダンス。ダンス。
男女が一組になって、ワルツでもなく、チークでもなく、
その時の音楽に合わせてリズムをとっていく。
こ、こんなことなら、ちょっと練習しておけばよかった。。。
伝統なんですって。
男性は、曲ごとに別の女性と踊って行く。
最後は、男性側からのジンクイエとありがとうの挨拶と、手にキスをで終わる。
わたしは、パートナーとこの披露宴に参加していなかったので、
おじさま達と踊った、踊った。
こ、こういう時はセクハラと思わずに踊るものです。
なんかこーいうのもおじさま達の楽しみになっているみたい。
日頃の労いもかねて、サービス、サービスと思いつつ。
12時の深夜にケーキカットが行われて、
その後は、花嫁さんがブーケを投げる予定になっていたのですが、
その時の介添人が彼女の妹さんで、次の候補生として妹にブーケが渡りました。
花嫁さんのブーケがなにがなんでも欲しかったのですが、
それができなかったので、次のゲームに参加。
椅子とりゲームでした。
3人の大男と、2人の女性が争うことに。
もちろん参加させていただき、たぶん音楽もちょうどいいように
切れるようにしていただいたのでしょう。
一番最後まで残り、戦勝品をいただきました!
ひえひえにひえた
ウォッカ。が差し出された時は
呆然とその品をみるわたしでした。
だんなの方から前々から言われていた言葉は、
どーしてもっと長くいることができないの。
だったのだけれど、
最後の日に同じ言葉をお母さんからきいて
いや、いろいろやることがベルリンであるとか理由つけられることなのだけれど、
そういう理由を聞くために聞かれている質問ではないと思って
答えに困った。
多分彼はお母さんからそんな言葉を聞いて育ったんだろうなと
思い、だからこそ彼は自分の意思で実家にいて、働き盛りの今
家族4世代の大黒柱としてあるのだなぁと思った。
プロシエ、どうぞ、どうぞ。
という言葉が耳についたこの週末でした。