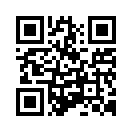年末にある方にインタビューしました。
彼女はたぶん、私が知っている人のなかで、
アメリカンドリームならぬ、
ベルリンドリームを手に入れたかただと思います。
アーティスト。
彼女と出会ったのは,数年前
あるアートフェアで、
私はわたしのブースで働き
彼女は彼女の作品が出ているミュンヘンのギャラリーのお手伝いで
ブースにいた方。
搬入や搬出、出品者のためのパーティーなどで会い、
ベルリンに住んでいる事、彼女のアトリエがミッテにあることなどをその時聞き、
オープンスペースのようになっている、彼女のアトリエを当時訪ねたものだった。
それが数年前の話で、
去年のあたりから
彼女の名前を新聞の一面記事に見るようになった。
発見した時は、自分の目をうたがったほどだ。
あのココ・クーンかと。
名前が珍しいので、間違いなく彼女であると分かった。
コンセプチュアルアーティスト。
と呼んでほしいと前からも言っていたし、
今もそうだという。
たしかぁ。コンセプトが入っているような
作品をつくっていたとおもうのだけれど、
ここだけの話、あまりこれ!という作品は創ってなかった印象の彼女だったので、
こんなにライバルの多いアート界で大丈夫なのでしょうかと、思ったことがあった。
すごくいい!でもなく
すごく!悪いでもない。
こういうのって本人が一番困るのだろうなぁと思いつつ。
でも彼女はやってのけた。
すごい!
彼女の立体作品で名をなしたのではなかった。
ベルリンのウンターデンリンデン沿いに
昨年10月末にオープンしたのが
テンポラリークンストハレというもの。
テンポラリー、つまり期間限定のアートホール。
2年間の限定で、というのは
そこにのちに東ドイツ時代に全壊されたベルリン城が建つので、
工事が始るまでの期間、アートが展示できるような仮設ボックスが出現したのだ。
仮設といっても、かなりしっかりした建築物だ。
仮設感がない。
クンストハレをやろう!と言い出したのは
ココ・クーンであった。

そして現実化したのも彼女とその仲間の力であった。
もちろん、思い付きのみでこれは出来上がったものではなく、
このアイディアには下敷きがあった。
去年の終わり頃のニュースの一つに
パラスト・デア・レパブリックがすべて解体されることがあった。
旧東ドイツの国会議事堂である。
統一後はその役目もなくなり、建築時に内部に使用した
アスベストが問題になり、その排除のための工事がずいぶん長く行われていた。
結局、ベルリンの約半分の人々たちの思い出の場所は、簡単に言うと
やはりアスベストを除いても、使い物にならないという西側の思惑で
取り壊される事に。
脇道にそれるかもしれないけれど、
今年、壁崩壊20年だから、そのパラスト・デア・レパブリックって
役目がなくなってからも、いろいろいじくられつつ、20年もただ佇んでいたと
思うとなんかすごい。ベルリンの一等地にある現代の廃虚だった。
まただんだんに時間をかけて取り壊されていったから、
世界の歴史にはこの完全消滅日は残らないのだろうなと。
これも計算されていたのだろうか。
そのパラスト・デア・レパブリックで、
アスベストの除去作業が終わった時点、壁という壁はまったくなくなって、
鉄骨しか見えなくなっていた時、そして取り壊すことも決定された時、
FRAKTALEフラクターレという展覧会が2005年9月から11月に行われた。
これはパラスト・デア・レパブリックに入れる最後のチャンスと言われ、
アートに興味がない人でも
一度はこの廃屋に入ってみたいと思う興味本位の人、
あるいは昔の権威的建物をもう一度拝みたいと切に願っていた人などが
この展示には足を運び、観客動員数的には成功をおさめたものがあった。
その展示には、私も足を運んだ者の一人であったけれども、
もう取り壊すと決まっている建物だというのに、
その建物の一部にどどーんとホワイトキューブが出来上がっていた。
それは„36x27x10“mという巨大な空間で、
わたしなんかは実はその中で展示されていた作品よりも、
その潔癖とした四方の白い壁の方に感動をした一人でもあった。
それが、もっと情熱的に感動した人がいて、
それがココ・クーンだったのである。
彼女はこのホワイトキューブを是が非でも残したいと願って、
もうこれで入場終わり!といっているパラストが
まだその年の12月までどうにかなることを知り、
友達のアーティストに熱心に声をかけつづけ、かけつづけ、
アーティストと展示作品を集めて、
最後といわれた展覧会の次に最後の最後の展覧会を
オーガナイズしたのだ。
これは2週間の準備期間しかなく、友達のつてで
それでも36のインターナショナルで活躍している著名な作家の作品を集め
11日間にわたって展示し、主催者も驚く
のべ1万人の入場者があったというものであった。
この展示の成功にかかわらず、
この白い壁とパラスト・デア・レパブリックは
取り壊される運命に。
けれどもココはあきらめず、
ベルリンにベルリンからのアートを展示するホールを夢見て
最後の最後の展示にきた観客の中に
このホワイトキューブを残すという自分のアイディアに興味をもった投資家をみつけ
ローコストでプランを立てられる建築家をみつけ、当時そのベルリン城跡に短期間
施工されようとしていた都市開発計画とアートホールを結びつけるような設計を
提出させ、そのプランを市に通し、また市から建築許可をもらい、
実際2008年に建物を現実かしてしまった。
もちろん彼女一人の作業ではなく、
よりよいチームワークが成せる技であった。
どうしてこんな大事業を大成させることができたのですか
という質問に。
彼女いわく、
できるかわからなかったけれども、この事業のことを話す時は、
本当にわたし情熱的だったの。
もう最初っから。
の答え。
彼女のお父様は建築家だったかと記憶している。
その血が流れているのだろうか。
実際のコンセプチュアルアーティストと自称する彼女は、
こつこつ、一つ一つ作品に向き合うというタイプではなく、
人を巻き込みながら、自分のコンセプトを形にしていく人ではないか。
なんだ、今までは器が小さすぎたのかしら、
それでその力量を発揮できなかったのかなとも
思う。
ベルリンはねぇ。まだやれるのよ。
よい友達とアイディアと実行力があれば
できるまち。
他の大都市をご覧なさいよ。
この内の1つ、あるいは2つ、もしくは3つも揃っていても
出来ないことがあるわよ。
ここはできる。
行動あるのみ。
と。
とにかく、私とのインタビューに2時間つかって、
さて、帰らせていただこうかと思った時、
また新たなインタビュアーが来るという状態。
彼女、セレブっぽくなっちゃった。
でもココまでの成功物語は聞いた事ないから、
本当に聞くのを楽しませていただきました。

写真は右がその話題のクンストハレ。遠いですが巨大です。
左はそのクンストハレの裏手にだれがつくったか、まねっこの箱が。単なるコンテナ。
こういうのもよく考えてやっちゃうと思うね。ベルリンの人。。