ドイツと日本とよく比べる事があるのだけれど。
それは、ドイツの社会で不甲斐なく思った事があったり、
日本から今まさに来た、日本の方と接してして、
忘れられた感覚が呼び覚まされたことがある。
なんか全体として、思うのだけれど。
ドイツは祖国の表現として
Vaterland(ファータランド、父の国)
っていう表現があるし、
日本は、母国っていう表現がある。
(Mutterlandという表現があるけれど、
辞書をしらべると植民地に対して本国の意味だから、
母国と同等には扱えないと思う。)
とにかく、祖国とか故国という表現方法に
父と母、どちらかを使うということがいえる。
これは、言葉の成り立ちの問題を考えると
父方よりとか、母方よりの感覚があったからこそ、
出て来た言葉ではないか。(とても唐突な発想です。裏付けはありません)
このキリスト教国で父の国というと、
父、子、精霊の三位一体を思い出し、
精霊はどの性別かわからないけれど、子は息子という意味であるだろうし、
これらに女性らしき影がみえない。
また、ここでの理想的な父親の性格を表すのに
旧約聖書のイサクの犠牲の話を思い出すのは私だけだろうか。
父、アブラハムは、神から彼の信仰心をためされ、息子イサクを犠牲に差し出すように求められた。
アブラハムは、神に従い、イサクを殺そうとしたところに、彼の信仰心が確かめられ、
神はこれを止めた。
アブラハムの潔さと
思い切りのよさ、ゆるぎない決断に究極の父性を感じる。
この話は聖書の中の話であるし、
実際、子供を犠牲にできるのであろうかと、
彼の神経をも疑うけれども。
父性の原理は「切る」ということを考えると
なにものもふりむかず究極のところまでいけるという度胸とその態度に
ヨーロッパの厳しい父性の基礎を感じるのです。
そういえば、ドイツの女の子はおやじさんぽい。
JaかNeinですぐ答えられし。。時には、結構威圧的だしぃ。。
日本は、それにくらべて全体的に女性的かなと思う事も。
女性の原理は、「包む」のであるならば、
それれは全体をまとめるという良い方向もあるけれども、
また飲み込まれてしまう危険性もあるでしょうねぇ。
切られないように、飲み込まれないように
やっている自分が2007年いたように思えます。
でも、まだまだですねぇ。
そうかぁ。今はVaterland、ファーターランド、父の国にいるんだなぁ。
と思う次第です。
2007年、ブログを読んでいただいてありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします!!
ぼのぼの







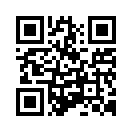
この記事へのコメント
うーん。うなりました。
アブラハムがどーんと出てきましたね。旧約聖書とは。
わが祖国、と口にしてみると、どうもしっくりこないですね。
わが母国、というほうが、まだましかなあ。
どっちもいまいち、なのがいかにも日本流なのかしら。
キリスト教国における神なる父、子、聖霊の三位一体。
現代日本における父性原理の欠落と母と子の関係。
太古、女は太陽であった、とするなら、
これまたこんがらがってくる。アマテラスは母たる神だよね。
明治維新以来の国家神道の分析が、いま、必要になっているのかしら。
母性の蔓延はなんでも包み込み、管理でがんじがらめにし、鎖を断ち切って食いちぎって荒野に飛び出す青年たちの根を腐らせる。
企業体というものも、この点、母性の化身といえるのかな。
企業に属すものと、その家族の面倒までみてしまうという大日本株式会社のありよう。さらに、オフィスラブで結婚とくれば、結婚斡旋までしてくれてしまう、小姑日本企業。怖い気もしますね。
悩みつつ、これからも前に進みましょうや。
今年もお世話になりました。このブログにも大変感謝。
来年はも少し、書き込み多くするよ。
特にドイツ人って、啓蒙精神がかなり効いてるというかんじがするねえ。
あるドイツ人女性がティーンネージャーで一人旅にでた理由を述べたことがあるんだけど、「1人で生きて行けるってのを感じるために出かけたの」っていう自己啓蒙の力はすごいですなあ。
女性が背伸びせずに社会で個人として見てもらえるように来る日はいつだろうねえ。。。
ぶつぶつ、ぶつ子。
お二方。
私の書いた事もなんだか立証に基づくものでもなく、感じた事や、日々刺激されることからつつつつと書いているだけで、あまり自信がないのだけど。
正直な共感を得られるのは、なんかあるのかなぁ。
でも社会の内容が結構複雑で、世の中も結構複雑になって、
いろんな考え方があるじゃない?それに男はすべて男らしくて
女はすべて女らしくっていう訳じゃないじゃないー。
一言で言うと簡単だけれど、個々のやりとりは色々あるからねぇ。
男の人も背伸びして疲れちゃっている人もいると思うよ。
ちょうどいいバランスっていうのがあればいいよねぇ。
背伸びしなくても一緒にやていけばいいじゃん。
母と父っていうものは必要なものだし、
男と女っていうものも。
両立っていうものをどーにか受け入れられることができたら
いいんじゃないかなー。
それができれば、少々の苦労はあってもやっていけると思うんだけどぉ。。
実際、意地やプライドってものが邪魔しちゃうかもね。
むずかしいねぇ。
ラテンはマリア信仰か、
なるほどねぇ。そうなると、なんとなくmisaっちのつきあい方の基本が
分かるような気がする。
日本だと、観音信仰の精神っていう感じかなぁ。
そういう感覚の人いるのかなぁ。
(基本的に観音様は女?男?っていう疑問がのこるけれども)
自己啓蒙ねぇ。すごいねぇ。
そのティーンエイジャーの彼女の一人で生きて行けるっていいう
感覚とはちがうのだろうけれども、
一人でねぇ。生きるって。。実はあんまり出来ないねぇ。
あんまり気にしないで、前にすすんでいきましょ。