http://nishiokanji.com/blog/
西尾幹二さん。
ドイツ文学者からの出身であるのに、
ドイツと日本の架け橋になる以上の幅広い領域に渡って活躍されている。
日本に揺さぶりをかけている数少ない知識人のうちの一人ではないかと。
ヨーロッパと日本の比較は、彼の歯切れのいい文章から参考にさせてもらうことが
多い。とても的をついた分析と解説で、私の体験と重なり、うなずくポイントがふんだん。それが例えば70年代に書かれた記事で、現行のものでなくても、色をあせていないのに感動。実際、彼のヨーロッパ人への分析を指南書として使わせていただいております。
例えば、家の構造についての分析。
日本は、ほんとうの意味での私室というものを持たず、家に家族が寄り添って住まうという形態を持つ。この場合、家全体が私的であり、外部の公共とは隔離が成立する。一方、ヨーロッパでは私室というものを持ち、この個室を出た途端に、例えそれがまだ住んでいるアパートの内部の廊下であれ、公共という概念になる。つまり、公共生活がより身近なのである。この公共生活はさらに住んでいるアパートからすんなりと外に出て、街のつくりとなっていく。だからこそ、主要な通りは、皆があつまれる公共の広場に繋がっているし、皆が集うような場所、市役所や中央教会は、オープンな場所であり、垣根はない。唯一あるとすれば、それは街を囲う城壁だろう。そこで、外敵に対しての厳しい態度があるという。
ここまでは要約で、以下、要約できないような強い表現なので原文から引用。
「市民が家族よりも、公共生活を重視するのは、城壁の外の異質物に対する警戒心と団結心から発していることは明かであろう。逆にいえば、外敵に対する用意から、市民のひとりびとりに対し、公共に生きることの要請がある。社会に対する責任と、自由の制限は、ヨーロッパ市民社会の2つの要件であり、それはまた、市民が個人の自由の無制限の拡大が何を意味するか、その恐ろしさを知っているという意味でもある。」
今私はWGという他人と共同生活を始めたばかり。
ベルリンに長い事いて、こういう体験は始めてなのだが、そういえば、ちょくちょく周りに引越のお知らせをしていて、日本からの友達から、開口一番に、WGはうまくいかないだろうと、一人ではなく、何人かに予測されていたものだ。
彼らもWGの経験や、日本人の友達のWG談を聞いていて
おそらくあまり、ポジティブな印象を持たなかったのでそうアドバイスをしていただいたのである。
でも、このWGネガティブな印象は、西尾さんの分析を頼るなら、おそらく公共についての枠組みの違いではないだろうか。日本人はおそらく、玄関を入ったら、キッチンやお手洗い、共同の部屋まで、私的な空間と考えるだろう。でも、ここでは、自分の部屋のみが私的な空間を許され、あとは公共の感覚なのではないか。そこに思いの行き違いがある。元の原因が分からないと、誤解も生まれ、偏見も生まれやすくなるのではないか。とこの文章を読んで思った次第である。
さぁて。私の私室は、約6帖の部屋。ベルリンで東京一人暮らし生活の気分。
やれやれ、理論でわかっていても、私のWG生活どうなりますやら。
しかし、西尾さんの文章は、強いねぇ。
常に挑発的な彼の発言や、本のタイトルに、脱帽する。
あれだけ勇気をもって、自分が発言したことに対する非難・批評を受けて立つ人はいないだろう。世相をかき混ぜる事によって、鬱憤を喚起させる。いやいや、こんな表現、国語的にあってないと思うのだけれど、なんだかお祭りによって、昔の人が日頃の鬱憤を晴らしていたようなイメージで、カンフル剤のような効用が。奮い立たせる感じで。
彼のブログを読むと
今では、書かなければならないことと、時間との戦いだとか。
常に戦っているその姿勢に敬服。
彼の本をアマゾンで探していたらこんなのもでてきた。
男子、一生の問題
—「毒にも薬にもならぬ人間」に魅力はない
このタイトルですでに喝破した感があって、
この本の彼の書きっぷりを読んでみたくなった次第です。
「男子、一生の問題」
というよりも、
私はどっちかというと、
“「毒にも薬にもならぬ人間」に魅力はない ”
の副題に反応した方です。

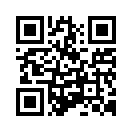
この記事へのコメント