プログラムからはカールソン・チャンがキュレータとして
アジアの美術についてのトークショーによばれていた。

彼は、香港生まれだけれど実際育っているのはカナダで、
アクチュアルなアジアの現場で起こっていることについてはあまり知らない。
そんな彼に最後観客から
「あなたは、香港生まれで、カナダで暮らされ、そして今はヨーロッパで活動しているので、
結局アジアで実際何が起こっていか語れないとおもいますが、この状況をどう思われますか。」
という質問がでた。
これは、彼に対する批判でもなく、トゲのある質問でもない。
どう、西洋的な環境で育って、今もその環境にいる
彼がアジアをどう代表しているのか不思議に思っての純粋な質問である。
カールソンは、
今、私たちはアジアという枠組みで企画されたトークショーに参加していますが
実は、私が思っていることは、大事なのはナショナルパーソナリティではなく、
パーソナリティであると。私は、個人を代表してここにあるのであって、
ナショナルパーソナリティとしてここにいるのではない。
と答えた。
左隣にいた、中国から招待された女性の中国人のキュレータが、
私も同感であるとすぐにマイクをとって言っていたのが、
カールソンの意見をものすごく後押ししていた。
彼女は中国を代表して来たように見えたが、
自分のパーソナリティをも代表して来ているのだろう。
中国では今アートがお金に結びつきやすく
浅はかな知識で売買され、バブルを呼んでいると。
その勢いがすごいらしい。彼女は小さい体ながらも警鐘を鳴らしていた。



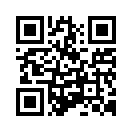
この記事へのコメント
最初ドキッとしちゃったけれど、
どういう展開になるんだ!!!と。
でも、やっぱり「国際的に」生きてきたバックグラウンドを持つ人は
私の旦那を始め、国籍に頓着しないことが多い。
私は日本生まれだし、日本で育ったし、この感覚は
本当にいまだ理解しずらいけれど。
この感覚は、子どもの成長過程に
どれだけ世界というものを見てきたかによるのかなと。
というのも、海外生活が長くなっても
やっぱり日本人としてのアイデンティティは消えないし
実際濃くなってきていると思う時もあるくらいだもの。
子供のころの育った環境がものすごーくその後の人生に影響しているよね。
3つごの魂っていうけど、本当なんだよねぇ。
さすがっ昔の人の言う事は違うよねぇ。
2001年の広告批評4月号が手元にあったので読んでいたら、こういう内容があったよ。2001年の時で古いけれど、“いま言葉を書く”っていう月のテーマがあって、その中で“言葉の力ー言葉の引力、重力、遠心力”というタイトルの谷川俊太郎さんと天野祐吉さんの対談がおさめられていたの。その内容もすばらしいものなのだけれど、最後に天野さんが谷川さんにこう問いかけをするの。
谷川さんは前に、携帯電話をみんながつかうのは、人間の声をみんな聴きたがっているんじゃないかとどこかで書いていたのですが、という問いかけにそれは寂しいからではないかとして、つづけるの。
谷川 「僕は、キーワードは「寂しさ」だと思う。携帯電話だけじゃなくて、日本の現在の社会を見た場合に、ようするに大家族的なものはとっくに壊れてしまって、地域共同体もなくなっている。会社が「家族」だったけれど、その会社も壊れつつある。ほんとうの意味での家族のほうも解体していて、日本人は西洋的な「個」というものに直面せざるを得ない。だけど西洋的な個ってものはわれわれは持たない。だから、日本人はみんな、ある共同体を求めて、すごく寂しがっている。。。。」だから、ケータイがその寂しさを紛らす手段になっているのでは。。と続くのだけれど。今じゃ、ケータイじゃなくてメールとかウェブ上のやりとりになっているかもね。
そう、私が注目したかったのは、日本人がもともとはもっていない「個」に直面せざるを得ないという状況になっているということ。これには同感。カールソンは、すでにパーソナリティで勝負しようとしている。これは子供のときからの国際的な影響もあるのだろうけれど。逆に言えば、個でしかやっていけなかった、という状況が彼のパーソナリティというものを叩き上げ、練りに練り上げていたのだろうねぇ。現代というものは、個を見せられる時代だし、逆にいえば、あんたそれでなにやってるのー。と個を見せないとやっていけない時代でもあるような。結局、堂々としていることが大切なんじゃないかなー。“主婦”や“主夫”やってまーすでも。それでもいいと思うよ。やることやってるんだったら。
日本人が、もともと不慣れな個、つまり自分自身に向き合い、それをまた人に伝えていかなければならないというとき、不慣れは不慣れななりにまた工夫をこらしてできるようになると思うのだけれど。
それは、また古い枠というものと新しい枠というものを“自らの判断と表現力”で使い分けていくことにも通じるとおもうのだけれどー。
熱くなりました、失礼。
谷川さんが表現しておられる“個”というのは、
孤独とか、孤立にむすびつくような団体とはなれての個という意味かなー。
パーソナリティとはまた違う意味でつかわれているのかも
しれないと思いはじめました。
コミュニティサイトと言われるものが浸透したのは、まさに日本人の孤独を癒してくれたからだと私は思ってる。面と向かった人間関係の中に、リアルな繋がりを感じにくい世の中で、それも毎日忙しく、そして毎日やるせないことが起きる。このやるせなさや忙しさは他の国に居ても感じることはあるけれど、日本では個々の繋がり方が変わってしまったから、それを支え合える「リアルな仲間」が見つけにくいのは確かだと思う。
個が基本の欧州文化で育った彼らは、ある意味タフなんだと思う。そして、他人との距離の取り方や支え合い方を取得済みというか。協調や調和のしかたや構造が違うよね。単純に「道徳」の授業をとってみても、私たち日本人は常に他を意識しながら意見を発していた気がする。そして、おおかたにして意見は発されないことが多かった。「考え中です」と。そこで何も注意したり、生徒が意見するように差し向けたりしない先生も道徳のメインキャラとして記憶に濃い。全員があまり楽しんでなかったよな。それに反して、欧米人の学校でこう言う授業は、ディベートとかディスカッションとかのくらすがあるとして、きっと白熱したり、しみじみみんなで考えたりということが繰り広げられるんではないだろうか。
ドイツに来て最初の頃、ぽかーーーーんとこう言ったディスカッションまでもいかないような、会話のキャッチボールを眺めていたのを思い出す。単純に語学レベルが原因なのではなく、言うことがない!頭空白。「考え中」の自分。いまだこの筋肉はトレーニング中であるけれど、カールソンのような人間に生で会うと本当にびびっと刺激される、この筋肉。
すごーく考えさせられる内容でした。うーーーん。こんだけ書きまとめられるのはすごいなぁ。これを読んで、「考え中」やっておった。
そうだねぇ。リアルな繋がりが感じにくくなった。そうだと思うよ。でもリアルな繋がりってなんだろう?私にとってリアルな繋がりって、お互い忙しい身である中でも、親身になって客観的にみてくれたり、繋がるって言葉がついていても、それが必要だと思ったら私自身や、私の考えまでも突き放すまでもできる仲間かなー。突き放すってそんなにできないことだと思うよ。だって、よくないなーと思った事を安易に受け入れることより、かなりのエネルギーを必要とするもの。家族だったらもしかしたら、親も子も怒られ慣れしちゃっているかもしれないけれど、遺伝っていうものは強いと思うよ。だから、ちょっと不安に思うことや迷う事を家族に相談すると、自分のコピーが発言しているみたいになるんじゃないかなー。特に近い歳の兄弟姉妹なんかがいたら、二つ人生があったら、こういうふうになってたんじゃないかなんて楽しい事考えられるんじゃないだろうか。もちろん底の奥底の部分は同じ質がでてくるのだろうけど。兄弟がいない人や、歳が離れていたり、また住んでいる土地が離れていたりすると、やっぱり同世代の動向が気になるのではないだろうか。というか、協力、協調してやっていった方が得だと思うのよ。なにせ、彼らはおなじ時代をおなじスピードで生きている人々だから。その時代の経験と知恵は持っている。その点、受験戦争や、就職戦線を通過してきたものは、太平洋戦争を国民一丸となって経験した人々とは、ちょっとちがうのかなー。見えない敵との戦いじゃなくて、机を隣り合わせての戦いだったから。まあ、そんなに努力していない私がこういうのも変ですけれど。
そうだねぇ。ディスカッションとか大切だと思うよ。それから相談っていうのも大事だと思う。その人のアドバイスを受けようとおもって相談に改まって行くっていう感じじゃなくて、まあ、自分の中で話を押し出すっていうのもいいと思うのだよねぇ。その人がその自分で固めた話で前にすすめそうだったら。前、語学学校で先生が、「ああ、今から会議だ」ってため息をついていたけれど、その会議は新しい教科書を導入するかどうか。半年間も皆で相談しあっているの。様々な意見交換が行われて、それぞれ古い教科書がいいと思うチームといや、新しい方がいいぞっていうチームに別れて大ディスカッション大会。それを半年もつづけるのだから。その間にその語学学校での真相が見えてくるらしい、それで、最後はみんな納得して、新しいことに皆でトライするみたいなのよ。徹底的にディスカッションしていく。そこではその時のテーマの意見としてみんなケンケンガクガク。でもそれはそれで、あとで個人に対する恨みつらみもなし。皆できめたんだから、これでいく!っていう決定が最後に下って、みんなそれで行動していく。反対した人もそこで従う所がすごい。それは自分が納得いくまで議論したという誉めもあるだろうし、あきらめもあるだろうし、なにせでも反対していたものに対して、仕切り直ししてそこでまた教える楽しみを見いだしていくっていうすごさがあるねぇ。
ちょっと横道にそれました。
意見は意見で、ちょっとぐらい激しい意見があっても、それはそうだと受け止められる度量が必要だねぇ。と思います。なんか、中傷しない、っていうより傷つかなくてよい、の方に重点をおいてぇおれば、まずは自分を守ることができるら、とも思うのです。
それぞれの意見によって個が露になり、それでその露になることを恥ずかしいと思わず、しかも相手の個を探り寄せる感じでぇ。まあ、間違っていたら間違っていたで、素直に受け止め、あやまり。どうでしょう。こんなリアルで。