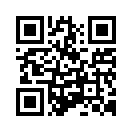企画&コーディネート&テキスト歴
〈展覧会企画〉
オーガナイズ —企画の立上げから全面的に関わったもの
コーディネーション —企画と作家をつなぐことに関わったもの
アシスタント —企画の補助
2005 Nov-2006 Oct アシスタント
„ベルリン—東京/東京—ベルリン 両都市の美術 “展
主催:ノイエナショナルギャラリー、ベルリン、ドイツ
2005 Jul オーガナイズ
„開発好明 発泡苑 “展
後援:日本大使館
主催:ベルリン東洋美術館、ベルリン、ドイツ
2004 Nov コーディネーション
加藤泉 アーティストインレジデンスプログラム
グロピウススシュタット、ベルリン、ドイツ
2004 Nov オーガナイズ
„Pro Tsubo坪あたり日本現代美術“展
後援:ミュンヘン日本領事館
主催:ノイエギャラリーランドスート、ランドスート、ドイツ
2004 Aug コーディネーション
コンサート “ミュージアムの長い夜”におけるアリアンツ社でのアジアナイトにて
クンストアリアンツベルリン、アリアンツ社、トレプトワ区、ベルリン
花代さんとラテンアジアポップジャズを
2004 Aug アシスタント
"So weit Japan−そんなに遠いの、遠くないよ日本”展
主催:クンストアリアンツベルリン、アリアンツ社、トレプトワ区、ベルリン
2004.7.7 アシスタント
七月七日にて、七夕風船プロジェクト、
シュプレー川を天の川にみたてた河内秀子さんのストリートパフォーマンス
ミッテ区、ベルリン
2004 May オーガナイズ
"Isst Du gerade meinen Tofu? −ちょうどわたしの豆腐を食べようっていうの?“展
ユーモア、アート、文化異差を越えたコミュニケーションについて
場所:バックファブリック、プレンツラワーベルク区、ベルリン
2003 Dec オーガナイズ
"Mirage−Beyond the light, Beyond the space "
逢坂卓郎、大塚聡 インスタレーション展
後援:日本大使館
場所:聖エリザベス教会、ミッテ区、ベルリン
2003.7.6. アシスタント
七月七日にて、七夕風船プロジェクト
シュプレー川を天の川にみたてた河内秀子さんのストリートパフォーマンス
ミッテ区、ベルリン
2003 Jun コーディネーション
大塚聡 アーティストインレジデンスプログラム
インゼルホンブロイヒ、ノイエス、ドイツ
2003 May コーディネーション
グロピウスシュタッド アーティストインレジデンスプログラム
ダンスグループ モノクロムサーカス 収穫祭パフォーマンス
グロピウスシュタッド、ノイケルン区、ベルリン
2003 Apr アシスタント
モリアートミュージアム"Young Video Artists Initiative" 巡回展
フランクフルト日本コネクションフィルムフェスティバルの開催にあわせて
場所:クンストラーハウスモノゾントルム、フランクフルト、ドイツ
2002 Nov オーガナイズ
„Pro Tsubo坪あたり日本現代美術“展
カイザースラウタン大学主催「日本講演週間」にあわせた催し展として
後援:カイザースラウタン大学、カイザースラウタン日本庭園協会、
フランクフルト日本総領事館
主催:テオドア−ツィンクミュージアム, カイザースラウタン、ドイツ
2002.7.7. アシスタント
七月七日にて、七夕風船プロジェクト、
シュプレー川を天の川にみたてた河内秀子さんのストリートパフォーマンス
ミッテ区、ベルリン
2002 Jun コーディネーション
ダンスグループ モノクロムサーカス 収穫祭パフォーマンス
カールマルクス通りアートストリート祭 "マギストラーレ
ノイケルン区、ベルリン
2001 Nov コーディネーション
air:伯林−前橋
前橋芸術週間におけるアーティストインレジデンスプログラム
ダニエラ・コマーニ、クリストフ・ケラー、ウルリッヒ・クレッチマン
主催:前橋芸術会館、群馬、日本
2001.7.7 アシスタント
七月七日にて、七夕風船プロジェクト、
シュプレー川を天の川にみたてた河内秀子さんのストリートパフォーマンス
ミッテ区、ベルリン
〈テキスト執筆ー雑誌〉
ミュージアムマガジン・ドーム(日本文教出版)
「博物館の長い夜」,Topics from the Museums in the World 2, Museum Magazine DOME,
June 2001, Volume 56
「政治&歴史&美術館−ライヒスターク」,Topics from the Museums in the World 5,
Museum Magazine DOME, December 2001, Volume 59
「オーストプロドクトミュージアム」,Topics from the Museums in the World 8,
Museum Magazine DOME, June 2002, Volume 62
「モノ博物館」,Topics from the Museums in the World 11, Museum Magazine DOME,
December 2002, Volume 65
美術手帖
“Over the Mirage”. Art on!, BT, March 2004, Vol. 56, No. 856
〈テキスト執筆ー展示カタログ〉
“GOOD LUCK!!現代美術の一様相” 展カタログ
“斎木克弘、現代写真家と現代首都、ベルリン(Katsuhiro Saiki a contemporary photographer and a contemporary capital Berlin)”, catalog “GOOD LUCK!! an aspect of Contemporary Art”, Tama City Cultural Foundation, Tokyo, Japan, 2002 (Japanese and English)
“Pro Tsubo” 展カタログ
“Was ist eigentlich”Pro Tsubo?” (“What does ”Pro Tsubo” actually mean?”), catalog “Pro Tsubo”, Neue Galerie Landsudt, Germany, 2004 (German and English)
“開発好明 発泡苑 “ 展カタログ
“Ein Angestellter der ADF (An employee of ADF)”, catalog “Happo Yoshiaki Kaihatsu”, Museum für Ostasiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin, Germany, 2005 (German and English)
“加藤 泉“ 展カタログ
“Paintings that get close to the "quintessence"”, catalog Izumi Kato, Galleria Astuni, Pietrasanta,Italy, 2005 (Italian and English)
“樋口立也 ここに無いものの息吹“ 展カタログ
“Michi Kusa – Pflanzen am Wegrand”, catalog “Der Hausch des Nichtvorhandenden(sent of no scent)”,Nassauischer Kunstverein e.V., Wiesbaden, Germany,2006 (German English and Japanese)
〈翻訳〉
カタログテキスト“Sumazo 2006 Katsuhiro Saiki & Christoph Weber“ from German to Japanese catalog “Katsuhiro Saiki, Christoph Weber SUMAZO 2006”,SUMA-Verein zur Forderung der europaeisch-japanischen Beziehungen im Bereich zeitgenoessischer Kunst (SUMA Association for the promotion of European and Japanese relations in contemporary art) ,Vienna, Austria, 2006 (German English and Japanese)